2018年も引き続き京都で非常勤講師のお仕事をさせていただいておりました。 毎週東京と京都を行ったり来たりして新幹線の中で読んだ本のメモ。
マインクラフト 革命的ゲームの真実
@jishiha さんがオススメしてくれたので読んでみました。 マインクラフトの開発者ノッチが、様々な環境を経てマインクラフトやMojang社を作るに至った経緯が描かれています。 日本語訳のせいないのか何なのかわからないけど、そうか、、、ノッチは同い年なのか、、、えっ、父親がヤク中?、、、こんな生活してたの?みたいな感じのノリでサササっと読めました。 ジャーナリストが書いているだけあって、マインクラフトの時期ごとの売り上げと他のコンシューマゲームの売り上げが比較されていたりと気が利いていて読みやすかったです。
Mojang社の売却前に書かれている書籍なので最近の事は書かれていない。ノッチ本人は自伝とか書かないかなぁ..
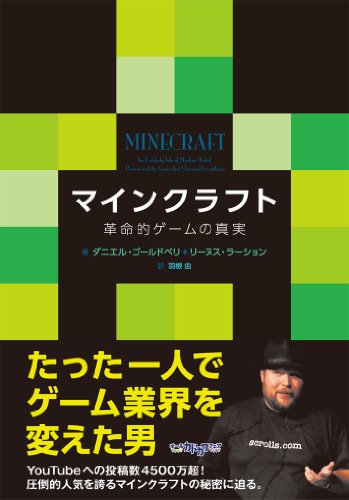 マインクラフト 革命的ゲームの真実
https://www.amazon.co.jp/dp/B00J4KD3K6
マインクラフト 革命的ゲームの真実
https://www.amazon.co.jp/dp/B00J4KD3K6「どこでもいいからゲーム販売店に行って、棚に並んでいる箱を見てみなよ。どれもこれもおんなじ調子だ。マッチョ野郎がでかい兵器をかついで、ほかのマッチョ野郎を撃ち殺すんだ。まったくステレオタイプで、うんざりするね」
タコの心身問題――頭足類から考える意識の起源
本屋で表紙のリアルなタコと目があって購入。
タコの心と身体の問題ばかりかと思いきや、時代はエディアカラ紀にまで遡ってマカロンみたいな形をした生物たちが進化の木をこう辿って分岐して…みたいな話を交えて結構広義な内容が書かれています。
うまいこと補足の情報を絡めてきたり、専門用語を説明してくれたりしつつ著者の感想が入ってきたりして、飽きさせないというか情報の配分のバランスがよくて話がトントン進むのでとても読みやすかったです。
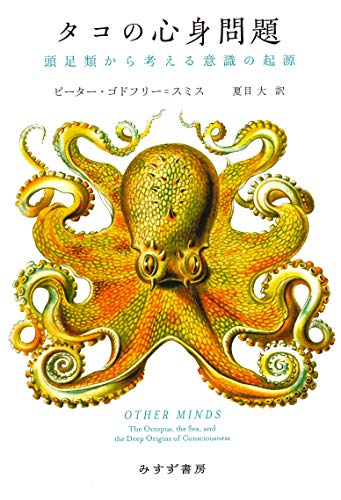 タコの心身問題――頭足類から考える意識の起源
https://www.amazon.co.jp/dp/462208757X
タコの心身問題――頭足類から考える意識の起源
https://www.amazon.co.jp/dp/462208757Xタコを含む頭足類は非常に優れた目を持っている。目のつくりは、大まかには私たち人間のものと同じである。両者の大規模な神経系はまったく独立に進化したのだが、どちらの進化の実験も「見る」ということに関しては、ほぼ同じ結果をもたらしたということになる。だが、目の背後にある神経系のつくりは、タコと人間では大きく異なっている。
紙の書籍しか出てなくて紙で買ったけど後からKindle版も出たみたい。
あなたの知らない脳 意識は傍観者である
脳が無意識下に行っている事象についてのあれこれが色々書かれてます。今選択しているこの行為は何十万もの世代を経るあいだに脳の回路に深く焼きつけられた成功プログラムの選択でしかない、みたいな話。
だとしたら今これを読んでアレコレ考えているこの意識とは一体…みたいな気持ちで色々考えていると怖くて寝れなくなった。とか書きたいところだったけど、そういえば子供の頃はこんな事考えて怖くて眠れなかった夜もあったような…スヤァ…みたいな感じでグッスリ眠れました。
なんて書いてたら面白くなさそうに見えたかもしれないですが、知りたい事、知らない事が沢山かかれていてかつ読みやすく、非常に良い本でした。
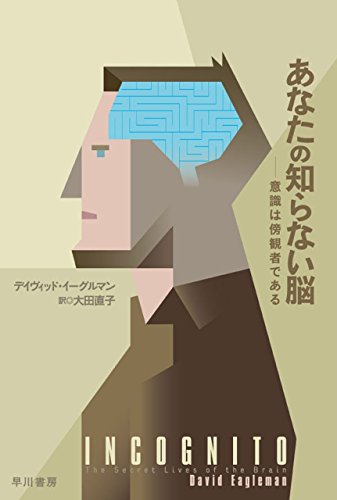 あなたの知らない脳 意識は傍観者である
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LW6ESHK
あなたの知らない脳 意識は傍観者である
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LW6ESHK一九六〇年代、ベンジャミン・リベットという科学者が、被験者の頭に電極をつけて、非常に簡単な課題をやるように言った。自分が選んだタイミングで指を上げるだけだ。そして高分解能の計時装置を見つめ、指を動かそうという「衝動を感じた」瞬間の針の位置を報告するように言われた。リベットは、人が実際に動くおよそ四分の一秒前に動こうという衝動を自覚することを発見した。しかし驚くのはそこではない。彼は被験者のEEG記録──脳波──を検討し、もっと驚くべきことを発見した。彼らの脳内活動は動こうという衝動を感じる前に生じ始めるのだ。しかもほんの少しではない。一秒以上前である。
この実験の話は衝撃的だったけど、でもこれ60年ほど前の実験なので今やったらどうなるんだろう。
細菌が人をつくる (TEDブックス)
先日登壇させていただいた Rails Developers Meetup では 発表資料 に突然脈絡もなく自家製ヨーグルトの自慢話を盛り込むくらいには乳酸菌の事を考えて生きています。
細菌群衆は指紋みたいなもので、マウス(PCを操作するほうのやつね)を調べたら90%くらいの確率で持ち主を的中させる事ができるらしいです。もっと上手く生育してやらないと…という想いから、細菌の本は隙あらば買って読むようにしています。
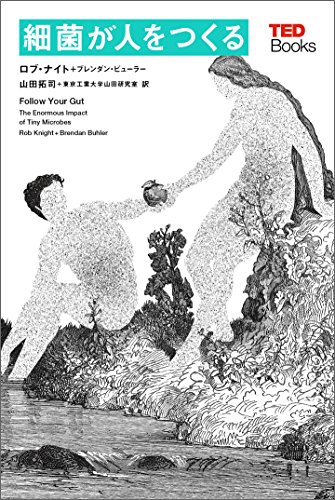 細菌が人をつくる (TEDブックス)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07DD6N81S
細菌が人をつくる (TEDブックス)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07DD6N81S顕微鏡でようやく見える小さな細菌がヒトの体内にどのくらい住み着いているか、ご存じでしょうか。 重さでいえば、平均的な大人には約1・4キログラムほどの細菌が住んでいます。脳とだいたい同じ、肝臓よりは少し軽いくらいの重さで、細菌群集(マイクロバイオーム) はヒトの体内でもっとも大きな臓器のひとつだと言えます。
折りたたみ北京 現代中国SFアンソロジー
紙の動物園 著者のケン・リュウさんがお勧めの中国SF作家の短編を選んで収録した短編集。面白いのもあったのですが、文化の違いなのか翻訳が悪いのか(中国語->英語->日本語みたいな翻訳なのだろうか)さっぱりなものもいくつかありました。表題作は映画化するととても映像映えしそうです(インセプションみたいな感じになりそうだけど…)。
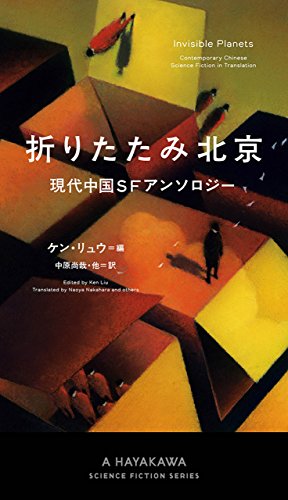 折りたたみ北京 現代中国SFアンソロジー
https://www.amazon.co.jp/dp/B079YRCKWM
折りたたみ北京 現代中国SFアンソロジー
https://www.amazon.co.jp/dp/B079YRCKWM判断のデザイン
デザインって自分の中にある様々な物差し(定量化できているものもそうでないものも含む)であれこれと対象を測ってみて、対象の本質を一番きれいに表現できる落とし所を見つける、みたいな作業なのではと考えているんですが、この書籍は「判断」、目に入った一瞬で解釈される物差しの上でどのように見えるか、見せるか、みたいな部分についてつきつめて考えられており、その辺についてじっくりと考える手助けとなりました。
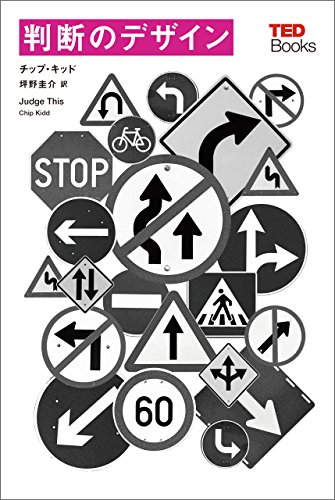 判断のデザイン
https://www.amazon.co.jp/dp/B073B3Z585
判断のデザイン
https://www.amazon.co.jp/dp/B073B3Z585“最初の印象を心から拭い去ることは難しい。一度紫に染められた羊毛を、もとの白さに戻すことなど誰にできよう?” —-聖ヒエロニムス(AD331-420)
ノモレ
アマゾンで主に取材をされているジャーナリストの国分 拓さんの著書。前作 ヤノマミ が面白かったので新作が出ると知って即購入したけど、こちらもやはり良い本でした。
最近の インタビュー記事 には「最後のアマゾン取材です」とあったので、もうこれが最後なのかぁと思うと非常に残念です…
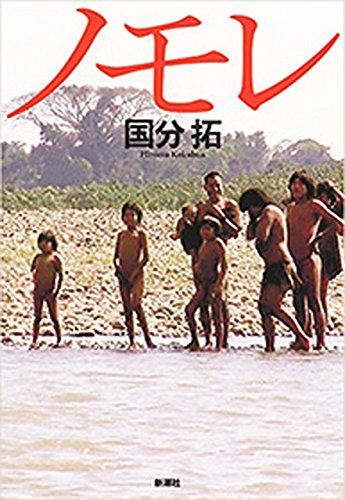 ノモレ
https://www.amazon.co.jp/dp/B07F7YGNZM
ノモレ
https://www.amazon.co.jp/dp/B07F7YGNZM二〇〇八年、メイレレスは世界的なNGOであるサバイバル・インターナショナルと組み、イゾラドの写真を全世界に公開した。それは、航空調査で撮影された一枚で、眼下のイゾラドが頭上のセスナ機に向かって矢を射掛けようとしているものだった。 確かに、衝撃的な写真であることは間違いなかった。 ニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、ル・モンド、タイムズ、APにAFP、朝日新聞など、世界中の通信社や新聞社が、赤や黒でペイントしたイゾラドが弓矢を構える写真を紙面に載せた。 しかし、イゾラド保護の世論を喚起するまでには至らなかった。結局、世界中の人々の好奇心を刺激しただけで、イゾラド保護のための予算や人員が増える結果とはならなかった。
サピエンス全史
周りに読んでいる人がちらほらいて面白そうだったので購入。 3章のあたりのホモサピが残虐すぎて同じ人類とはとても思えないんだけどたかだか数百年前の話だったりするし自分も生まれる時代が違ったらこうなっていたんだろうか… 読むのに時間がかかっていてまだ下巻の途中あたり。
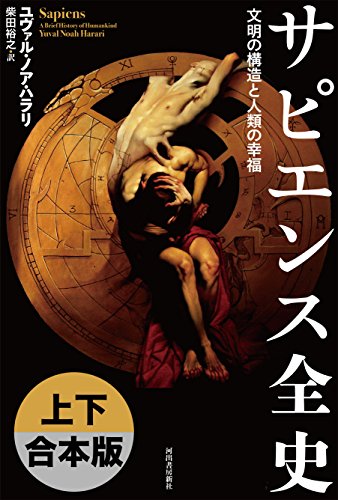 サピエンス全史
https://www.amazon.co.jp/dp/B01KLAFEZ4
サピエンス全史
https://www.amazon.co.jp/dp/B01KLAFEZ4今日、ほとんどの人が、私たちの祖先が剣を突きつけられて強制された帝国の言語で話し、考え、夢見ている。
さぶ
2018年は故あって引越しをしたのですが、引越しをした時に望月 峯太郎の ちいさこべえ をみつけて読み返していたらとてもよかったので(引っ越しの時って漫画とか読み返しちゃいますよね…)、ふと山本 周五郎は短編しか読んだことが無かったのを思い出して長編も読んでみようと思って購入。 不器用だけどまっすぐな登場人物達が非常に魅力的で、苦悩しつつも成長していく様が丁寧に描かれていて読んでいてとても引き込まれました。
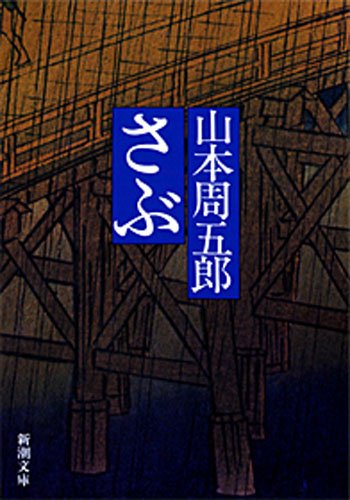 さぶ
https://www.amazon.co.jp/dp/B00CL6MWIY
さぶ
https://www.amazon.co.jp/dp/B00CL6MWIYそうじゃあない、岡安さんにかぶれたんじゃあない、こいつはおれの心の中で生れたんだ、これは大事なことなんだ
岡安さんはホント良い人。
日本婦道記
こっちは短編集。さぶがとても面白くて山本 周五郎分が物足りなかったので購入。
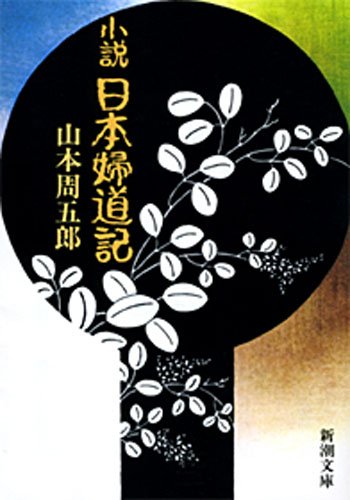 日本婦道記
https://www.amazon.co.jp/dp/B00CL6MWGG
日本婦道記
https://www.amazon.co.jp/dp/B00CL6MWGGハーバード×脳科学でわかった究極の思考法
脳科学の本が好きでよく買うからかレコメンドに頻繁に出てくるので購入してみました。タイトルが恥ずかしくてちょっと買うか迷いましたが… 事象と結果をかいつまんで効率的に摂取できるようにまとめてある感じ。結果ばかりが書かれていて、それがどういった因果で発生していて、今何故こう解釈されているのかとかを詳しく知りたい自分としては知りたい事がそんなにかかれてなくてちょっと残念でした。
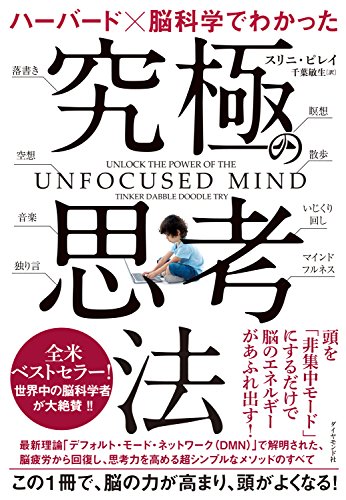 ハーバード×脳科学でわかった究極の思考法
https://www.amazon.co.jp/dp/B079XXH316
ハーバード×脳科学でわかった究極の思考法
https://www.amazon.co.jp/dp/B079XXH316脳は自分の選択を正当化するようにできている。そして、この脳の性質こそが、行き詰まりを抜け出そうとする懸命の努力を邪魔する。
死に山 世界一不気味な遭難事故《ディアトロフ峠事件》の真相
ディアトロフ峠事件 を題材にした本。 ディアトロフ峠事件についてはWikipediaとかで読んだので知っていたけど、出てくる地名はあんまり馴染みないものばかりだったのでGoogleMapで場所を調ながら読み進めました。 ホラチャフリ はこんなところ。 話は逸れますが位置関係とかを踏まえつつ本を読むと頭に良く入ってきますね。
事件だけじゃなくて時代背景や登場人物のちょっとした談話も交えつつ物語っぽく描かれているので読みやすくて、一気に読み終える事ができました。
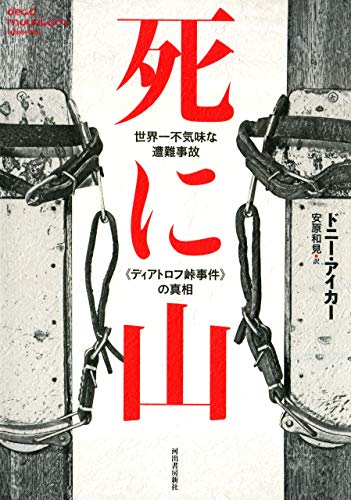 死に山 世界一不気味な遭難事故《ディアトロフ峠事件》の真相
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MQ134CV
死に山 世界一不気味な遭難事故《ディアトロフ峠事件》の真相
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MQ134CV政府のとった戦術のひとつに、再生できないレコードをレコード店にあふれさせるという手があった。その多くは再生できないどころかプレーヤーを故障させるという代物だった。そんなレコードには、音楽の途中に脅しの言葉が入っていたりした。知らずに聞いていると、いきなり恐ろしげな声で「おまえはロックンロールが好きなのか。恥を知れ、この反ソビエト主義のごくつぶしが!」と怒鳴りつけられるのだ。
以前読んだ「不自由な自由 自由な不自由」 でも思ったけど社会主義の時代の話は色々面白いエピソードがあって興味深いです。
2019年は講義が前期だけになるのでちょっと読書量が減りそう。
